世界の庭は幻のエデンを指向する(赤川 裕)
最近は先入観が取り払われてだいぶ変わってきましたが、
以前の私は「園芸植物」というものがどうしても好きになれませんでした。
なぜ?
それはまた、この次に。
今日は前回のつづきで、赤川 裕の『英国ガーデン物語 庭園のエコロジー』を読んでいきます。
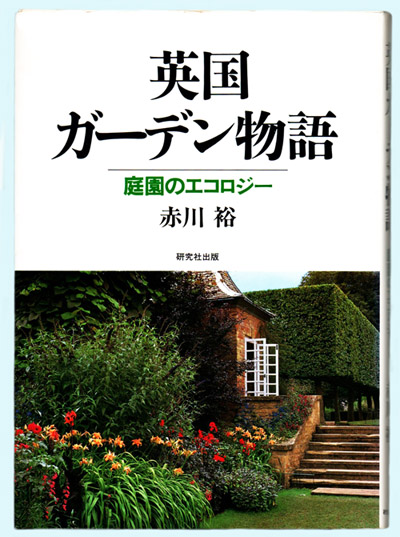
赤川さんは語源学的なアプローチから、最初の頃の「エデン」のイメージは、
「平原、広々とした草地」だったと考えます。
この「エデン」のイメージは、各地に都市が建設された12世紀頃をピークに、
「エデン」=「パラダイス」=「城壁に囲まれた空間」に変わって来ます。
熱砂の砂漠では、ひんやりとした土壁に囲まれ、
ジブリ(熱風)から身を守ってくれる空間こそ、
「楽園」のイメージでなくてはならなかったのだと思います。
それが「エデン」のイメージと重なり、エデン観に影響を与えます。
さらに時代は下り、都市がはらむ問題が顕在化するに従って、
人々の意識の中に囲われていない広大な草原へのノスタルジーが頭をもたげます。
こうして、本来別なイメージだった「エデン」と「パラダイス」は、
一度は同一視されたものの、ふたたび乖離し始めます。
ある意味、「エデン」という語が本来持っていた
「囲われておらず、広々とした草原へ開け放たれた空間」のイメージへと回帰して行ったのです。
私の見るところでは、世界の庭園史は、エデン性とパラダイス性という二つの座標軸の間に揺れながら位置してきたのである。それぞれの庭の作庭動機は、庭の数ほども異なるのであるが、個々の動機と手法が帰着するところ、作庭関係者がそれと意識しなくても、エデン的な庭の方向へ行くかパラダイス的な方向へ行くかという、二大要素の綱引きが見られると思う。
赤川 裕『英国ガーデン物語 庭園のエコロジー』
開放された空間である「エデン性」と、
塀に囲まれて内側と外側を遮断する「パラダイス性」、
この二つの要素の綱引きとして、赤川さんは英国庭園史を読み解いていきます。
現実はよく「荒地」や「荒野」に喩えられます。
大東亜戦争に敗北した日本に現れたのは、「荒地派」と呼ばれた詩人たちでした。
60年代だったかな、五木寛之は『青年は荒野をめざす』という小説を書き、フォークソングにもなりました。
前川清には『東京砂漠』というヒット曲があります。
「荒地」「荒野」「砂漠」、これらはいずれもつらく厳しい「現実」の比喩表現ですね。
「庭」は囲われることによって、外部=現実から遮断され、そこに身を置くことで、現実逃避、恐怖や不安や焦燥からの解放、心の癒しなどを手に入れることが出来ます。
これこそ「パラダイス」としての「庭」にほかなりません。
英国庭園は、一度は「パラダイス」としての庭を造りながらも、その後の英国庭園史を見ていくと、絶えず「パラダイス」としての庭を「エデン」化しようと試みて来ていることがわかります。
「閉ざされた庭」から「開放された庭」へ!
あるいは「閉ざされつつ、たえず外へ向かって開かんとする庭」へ!
それは「私」を「公共」へと押し出そうとする衝動でもあります。
「私」を守る心地よい「囲い地」を捨て、「公共」をめざす苦闘の道のりは遠い。「禁断の樹の実」は「知恵の樹の実」とも言われる。「公共」に向けて「私」を開く必要を「知って」しまったときから、いままで「「私」に安住していたことに罪の意識が生じ、「保護された私」に戻りたい心と「公共」に組さねばならない責務の心とに引き裂かれる。アダムとイヴは、そうした人間の存在様態の祖型として、今日もエデンの地平に向けて歩いている。
赤川 裕『英国ガーデン物語 庭園のエコロジー』
フランシス・ベーコンの荒地(ヒース)の庭、
ジョン・ミルトンの外の荒野、
アレキサンダー・ポウプの「他人のための木陰」、
「ナショナルトラスト」の創設、
〈シシングハースト〉の抜かれなかった雑草、
〈バーンズリーハウス〉の「荒地」(ウィルダネス)と見てきて、
赤川さんは英国庭園の本質をズバリ言っちゃってます。
イギリスのどの庭にも興味は津々であり、
オープン・ガーデンというシステムにも心惹かれますが、
もっとも私が「これがイギリスか!」と感嘆するのは、
「ナショナル・トラスト」の存在です。
これについては語りたいことがいっぱいあります。
でも、今日は長くなりすぎたので、これでおしまい!
人間が苦心の末に獲得した技術によって思いどおりの、自分だけの空間を手に入れる――これほどの贅沢はないが、その空間が心の願いを満たしてくれるという完全なまでの自己完結性は、素晴らしいと同時に「自閉」の極みでもある。これをあえて切り開き、「他者」のために差し出し、「公共」の中に「私」を投げ入れてしまう。こんな大きな犠牲はない。イギリス庭園のメッセージは、それをやろうと呼びかけているのである。
赤川 裕『英国ガーデン物語 庭園のエコロジー』


