スプリング・エフェメラル Spring Ephemeralと呼ばれる、一群の植物たちがあります。
キクザキイチゲ
アズマイチゲ
イチリンソウ
ニリンソウ
フクジュソウ
セツブンソウ
エゾエンゴサク
ヤマエンゴサク
ムラサキケマン
カタクリ
ショウジョウバカマ
などなど。
いずれも春一番に咲く樹林下植物たちです。
エフェメラルというのは“蜻蛉”のこと。
かげろうは谷川などの水の綺麗なところに棲息していて、羽化して数時間で死ぬものもあり、
「はかなさ」の象徴みたいな昆虫です。
そこからスプリング・エフェメラルは「春のはかない命」というような意味になります。
蜻蛉の幼虫は綺麗な流れの石の下に棲み、渓流釣りの時にその場で取ってよく餌にします。
イワナやヤマメの食いつきが抜群です。
そういえば渓流釣りにも暫く行ってないな。行きたい。

写真は私の庭のスプリング・エフェメラル「ショウジョウバカマ」です。
「猩々袴」と漢字では書きます。
「猩々」とは真っ赤な色のことで、冬場、この植物の葉が赤変するのを赤い袴に見立てた、と言うほどの名前でしょう。
漢字で書かないと意味のわからないネーミングです。
20年以上も前に山取りしたもので、それ以来春一番に、毎年やさしい色合いの花を咲かせてくれています。
これを採集した場所は山のちょっとした斜面で、
まばらな落葉樹の下に、一面に広がるミズゴケの中に群生していました。
それから2~3年して同じ場所に行ってみたら、ミズゴケごとすっかり姿を消していました。
原因は、斜面の上に堤が造られてしまい、斜面に水が流れなくなったためでした。
自然の生態系は、人が自然にちょっと手を加えただけで、すぐに大きく変わってしまいます。


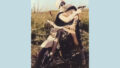
コメント