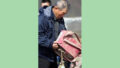ども。ミロです。
会津若松市の菅家市長が、かつての長州藩である山口県萩市を訪れるそうです。
18日に開かれる東日本大震災現状報告会で講師を務めるためで、
震災後の支援に対する返礼をかねての訪問となるようです。
会津藩と長州藩といえば、
幕末から明治にかけての戊辰戦争で激烈な戦闘を繰り広げたことで有名です。
この戦いは「会津戦争」と呼ばれています。
現在の福島県が主戦場となりました。
会津藩は、白虎隊に象徴されるように、
藩をあげて文字通りの「総力戦」で戦いました。
両藩(両市)はいまだに公式的には「和解」をしてないようです。
100年以上前の歴史的事件がいまだに忘れられることなく生き続けているとは
どういうことなのでしょう?
「会津戦争」そのものの「遺恨」というより、
戦後、会津城下には戦死者の遺体が山のように積まれ、
異臭を放ち始めるまで放置され、すみやかな埋葬がなされなかったといいます。
会津にはこのことに対する「人道上(武士道上)」の理由による「遺恨」が残っているようです。
そのことによって何らかの障害が起こってるわけではなし、
両市の協力もしっかり行われている以上、
そんな「こだわり」が残っているのも悪いことではないかもしれません。
たとえば、太平洋戦争後、
それまで「鬼畜米英」と呼んでさんざん戦って来た米軍が占領軍として乗り込んで来るや、
「解放軍」と呼んで大歓迎するような風潮があったことの方が、
よほど恥ずかしいことに思われます。
どちらも「日本人」の持つ精神的な側面であるのでしょう。
きょうは原発問題で御苦労中の福島県民へエールの気持ちを込めて、
「白虎隊」と「二本松少年隊」の歌を紹介したいと思います。
三田 明 『燃ゆる白虎隊』 1968年(昭和43年)
作詞/吉川静夫 作曲/吉田正 歌/三田 明
白虎隊というのは中国の「四神」思想から取った名称です。
古代の中国では、天の四方を幻獣たちが守っていると考えていました。
東の青竜・南の朱雀・西の白虎・北の玄武がそれです。
会津藩では、それぞれの名を冠した戦闘組織が作られていました。
白虎隊は16歳から17歳の武家の少年たちで組織されていました。
特に白虎士中二番隊20名が、
飯盛山で全員そろって自刃を遂げたことで有名になりました。
この時代の少年武士たちの気概、覚悟には胸をうたれますが、、
太平洋戦争時、
「死して虜囚の辱めを受けず」(戦陣訓)という形でこの「恥」の思想がよみがえった時、
近代物量戦のさなかでは、あまりに時代錯誤な教条主義としか思われず、
多くの兵の命の犠牲を生んだことを考えると、
複雑な心境にならざるを得ません。
もう一曲、「白虎隊」の歌を。
こちらの方が一般的にはよく知られていると思います。
霧島昇 『白虎隊』 1954年(昭和29年)
作詞/島田磬也 作曲/古賀政男 歌/霧島昇
「花も会津の白虎隊」の歌詞が泣かせます!
ひとりも逃げ出すものが無く、
少年全員が割腹自殺遂げたわけです。
これぞ会津士魂!
まさに日本歴史の「花」ですね!
(ひとりが命を取り留めたことにより、白虎隊の最期が世間に知られることとなった)
「会津白虎隊」は全国的に有名ですが、
「二本松少年隊」まで知ってる方は、
よほどの歴史ファンか歴女であるか、もしくは地元の方でしょうね。
「戊辰戦争第一の激戦」といわれるのが、
二本松少年隊が守った二本松大壇口の戦いでした。
まずはお聞きください。
三橋美智也 『二本松少年隊』 1965年(昭和40年)
作詞/高橋掬太郎 作曲/細川潤一 歌/三橋美智也
江戸で西洋流砲術を学んだ隊長・木村銃太郎は22歳。
それに従う隊士23名は、白虎隊士よりも若い12歳から17歳で、
13、14歳が多かったようです。
二本松藩の主力は、奥羽越列藩同盟からの要請で、
日光、白河口方面の戦いへ出向いており、
新政府軍が二本松へ迫った時には留守の老年兵や少年兵たちで守るほかありませんでした。
しかし、木村隊長から鍛え上げられた少年隊士たちの西洋流砲術の腕は確かで、
破竹の勢いで進撃して来た新政府軍の脚が、ここ二本松でピタリと止まります。
それもつかのま、敵の薩摩軍はつぎつぎと援軍が到着し、
少年隊はしだいに圧倒的な数の敵兵に包囲されてしまいます。
ついに隊長・木村銃太郎は敵弾に倒れます。
少年たちは隊長の首をはね、
二人がかりで運びながら敗走を始めます。
城下に戻ってみると、すでに守るべき城は炎に包まれ、
城下は敵の占領下にありました。
少年たちは敵兵めがけて切り込み、
或るものは討ち死にし、或る者は捕虜となって、
二本松少年隊は壊滅しました。
明治元年7月29日、
会津白虎隊に先立つことひと月足らず前のことでした。
もう一曲『二本松少年隊』の歌を紹介します。
こちらの方が、作曲の古関裕而も歌手の伊藤久男も福島県出身ということで、
地元ではスタンダードということになるのでしょうか?
そういえば、白虎隊の歌手・霧島昇も福島県出身ですね。
伊藤久男 『二本松少年隊』 1957年(昭和32年)
作詞/野村俊夫 作曲/古関裕而 歌/伊藤久男
「夫降るも亡び、降らざるも亦亡ぶ、亡は一のみ、寧ろ死を出して信を守るに若かずと議輙決す。」(『二本松藩史』)
戦っても藩は滅び、降伏しても滅びる。
それならば戦って滅びることで、武士の「信義」を守ろうではないか!
こうして二本松藩は、新政府軍に徹底抗戦を決断しました。
これって、大日本帝国海軍が太平洋戦争を決断した時の論理そのままですね!
「戦うも亡国かもしれぬ。だが、戦わずしての亡国は魂までも喪失する永久の亡国である。たとえ一旦の亡国となるとも最後の一兵まで戦いぬけば、われらの子孫はこの精神をうけついで再起三起するであろう」永野軍令部総長の言葉(児島 襄『太平洋戦争』)
「会津白虎隊」と「二本松少年隊」、 かれらこそ真に「ラスト・サムライ」だったと思います。